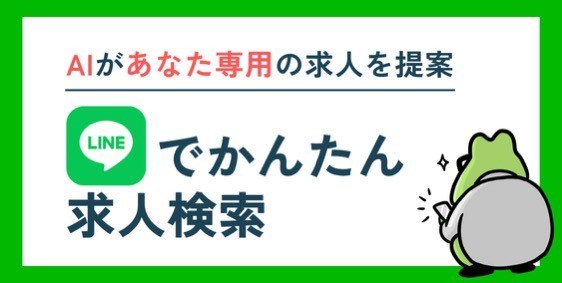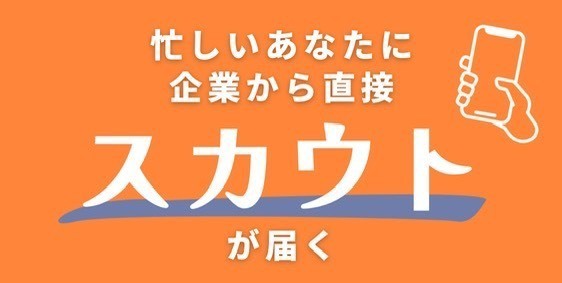Y.S.PARK パーク ヤン・スー 震源と、そのマグニチュード。【GENERATION】雑誌リクエストQJ1999年1月号より
大相撲に見たデザインの礎。

大相撲、である。
「鬢付油(びんつけあぶら)なんです。あれなら直せるんですよ。お相撲さんの大銀杏(おおいちょう)がヘアピンなしでいられるのは、鬢付油、つまりポマードの力ですよね。そして何回でも直せるんですね。ドライヤーもなくて直せる」
彼はさらに調べた。
鬢付油は誰がつくっているのか。
「島田さんという人がつくってたんです。後になってわかったんですけど、もう日本で一人しかいないんですね」
彼はサロンの営業を終えてから、島田さんの自宅を訪ねた。
「ポマード、つくっていただけませんか」
パークは、挨拶もそこそこにそう切り出した。
「なんだね、君は……」
島田さんは怪誇な表情で聞いた。
それが最初の出会いである。
「美容師、ねぇ。つくれないよ、そんなの」
それが島田さんの答えである。
それから、パークは通い始めた。何度も何度も通った。
しかし島田さんはもう断ったと思っている。当然、門前払いである。
パークはサロンの営業を終えてから訪れる。
夜である。島田さんは仕事を終え、風呂も終えてビールを飲んでいる。
そこに押し掛ける。
玄関は開かない。
真冬である。
パークは玄関先で立ち尽くした。
震えながら、立ち尽くした。
「髪の毛のデザインというのは重力との闘いだと思ってるんですよ。つくり込むヘアというのは、重力にどれくらい逆らうかなんですよ。で、一方で洗ったままの感じって、そのままの感じって、そのままですよね」
「ぼくはこう考えてるんです。自然というのはふたつあって、全くのナチュラルでボーンフリーというのがあるわけですよ。ボーンフリーというのはもうそのまんまですよね。で、その対極にアートレス。それはつくりこんでるんだけど、ナチュラルに見えるんですよね。これ、実は同意語なんですよ。ボーンフリーもアートレスも」
「見た目はナチュラルなんです。だけどアートレスは、アートしてレスしてる。つくってるんだけど、つくってるように見えない。で、ぼくはアートレスを選んでいるんですよ」
「じゃあ、アートするって何か。それはいかに重力と逆らうかなんですよね。単純に言えばね。髪を、重力に逆らって立たせることができればできるほど、デザインは選択の幅が持てる。音楽と同じですよ。3オクタープの声が出せる人は、1オクターブの人と比べると表現力が全く違うでしょ。つまりヘアデザインは、いかに重力を幅広くコントロールするかにかかってるんです」
だから、である。
だからこそ彼は島田さんにこだわった。鬢付油にこだわった。
「願えば叶いますよね」
真冬の寒空のもと、何度も押し掛ける美容師の姿とその意志の強さに島田さんは折れた。
こうして『Y.S.PARK』初のオリジナル商品となるポマードが完成するのである。
世の中にないから自分でつくる。
彼はポマードを3種類つくった。
つづいてムース、ミスト。そして最後にシャンプーからパーマ液までを手がけた。
しかも彼の多彩なプロダクトはすべて、「自分の作品づくりのため」という発想から生み出されている。
「人はぼくのことを“業界の村興し”って言ってます。この業界の中のあらゆる産業で、ぼくが入っていったとこが全部活性化するんですって。もうこれ以上ないだろうと言われていた成熟商品の分野が、活性化する、と」
ではなぜ、彼がつくるものは売れるのか。
考えてみた。
答えは簡単だった。マーケティングがないからだ。
メーカーは市場が求めるものをつくろうとする。
だから市場を調査し、分析し、売れるとなればゴーサインを出す。
あるいはすでに売れてるモノを探してきて、真似をしてつくる。
パーク ヤン・スーは違う。
彼は「自分が欲しいもの」をつくる。
自分にとって本当に必要なものが、世の中にないから自分でつくる。
売れようが売れまいが、彼には関係ないのだ。
つまりそこに市場の感覚は、ない。
あるとすれば、市場の欠落部分への意識である。
市場にないから自分でつくる。
それが結果的に市場の欠落部分を埋める。
だから、売れる。
当然のことである。
「レースをやってたころにね」と、彼は再び高校時代の話を始めた。
「ガソリンを変えるんですよ。普通、ハイオクってオクタン価が98くらいでしょ。当時、富士スピードウエイに行くとね、レース用のガソリンが買えたんですよ。それがオクタン価120。これだけでクルマの性能が20%も向上するんです。その実感があるから、道具ってすごく大事だな、と」
当然のように、彼は“美容のための道具”をつくり始めた。
「ぼくは絶対に世の中にないものをつくるんです。あるものをつくったらゴミになる。既存のものか、真似をしてつくったもののどちらかがゴミになる」
その一言が、彼の哲学を表現している。
たとえばブラシ。
彼がつくったロール・ブラシの中には楕円形のものがある。
それは髪を一度も落とさずに、連続して巻き続けることができるように考えた形状である。しかも、ブラシの太さのわりにはストレートヘアが簡単にできる。
あるいはいくつもの穴が空いたブラシ。
これはドライヤーの熱風がブラシに遮られることなく髪に当たり、速く乾かすことを目的としてつくられた。
「速く乾くということは腰を痛めない。しかも電気を無駄にしない。発電所の多くは田舎にありますよね。電気を使えば都会の空気は汚れなくても、田舎の空気は汚れるわけでしょ」
そしてコーム、である。
彼がつくったコームの素材は、スーパープラスチック。
高価である。
彼のコーム一本で、普通のコームが一ダース買える。
だけど、売れている。特に海外で、売れている。
なぜか。
「カットが早い人は、コームが熱をもって溶けてるんですよ。これはね、ある時に気付いた。髪が引っかかる。で、調べるとね、瞬間的に120度にまで温度が上がってる。マイクロスコープでコームの刃の根元を見るとね、溶けて三角形になってるんですよ。すると皮むき器ですよね。キューティクルむき器ですよ。美容師がお客さんのキューティクルをむいているんです。ある意味ではパーマより、溶けたコームは髪を痛める。で、トリートメントしましょうって勧めてるんですから、もうわけわかんないですよね」
彼はまず素材にこだわった。その結果が耐熱性に優れたスーパープラスチックである。
日本のメーカーやディーラーは「こんなのつくったら売れなくなる」と言った。なぜなら折れることがないからだ。
メーカーは折れることを前提に安い素材で安いものをつくり、代替需要で売上をあげてきた。
「でも、それこそ資源の無駄使いですよね」
パークの論理は明快である。
彼のコームの中には刃が丸く、しかも隙間が広いタイプのものもある。
「手櫛の感覚をそのままコームにしたんです。いま、いろんな人が再現性っていってるでしょ。だけどね、お客さんは家で手櫛ですよ。なのにね、平刃のコームで引っ張って、髪の毛引っかけて、カットしてるわけでしょ。その切り口に再現性がありますか?」
なるほど……。
しかし、彼のコームは見るからに隙間が広く、髪を引っ張るのはいかにも難しそうな形状をしている。
「髪の毛を引っかけて抑えることに慣れてる人は使いにくいでしょうね。でもそれはお客さんのためじゃなくて、自分のために道具を使ってるって人ですよ」
道具はお客のために、作品のために、デザインのためにある。
その道具を使いこなすのが技術だ、と彼は言った。
ライバルはディズニーランド。
時間はあっと言う間に過ぎていった。
彼の話は、そして目の前に次々と並べられる道具は、素人の私をも納得させるに十分な中身と説得力を持っていた。
ならばなぜ日本の美容界は、髪に優しく、デザインの幅を拡げ、仕事を速くして地球環境にも優しい『Y.S.PARK』の製品を使わないのだろう。
「たまたまウチに入ったインターン生から聞いたんですけどね。ある美容学校は試験の時に『Y.S.PARK』のコームを使うことを禁止している、と。その理由がね、速くワインディングができてしまうから他のコームを使う人と不公平になる、と」
「じゃあ、とぼくは思うんですよ。お客さんはどこにいるのか、ってね。道具が変わって速く巻ければ、それに越したことはないわけでしょ」
「業界のどこかにまだ根性シリーズがあるんでしょうね。本当は違うんですよ。作業なんか速い方がいいんですよ。だってお客さんはパーマのプロセスにお金を払うわけじゃない。できあがったヘアデザインに対して払うだけですもん」
ああ、日本の美容界……。
「ぼくは美容室って一軒一軒が異業種だと思ってるんですよ。たとえば髪が伸びて、目に毛が入るからカットするというのもあるし、かっこよくなりたいからカットするってのもある。だからね、ぼくは美容室をライバルだと思ってない。だって異業種だから」
「でね、ぼくがライバルだと意識してるのはディズニーランドなんです。あそこのパスポートチケット。美容の料金と同じくらいじゃないですか。で、どっちが気持ちいいか。帰り道に、あぁ来て良かった、と。どっちが思われるか。ぼくはディズニーランドの帰り道と同じくらい、そう思ってもらいたいと考えてるんです」
「ディズニーランドと他の遊園地ってね、95%までは同じなんですよ。だけど最後の5%が決定的に違う。その違いはね、デイズニーランドは裏に回ってもデイズニーランドなんですよ。建物の裏までいっても。でも他の遊園地は、裏に行ったら物置なんですよね。サービスもこだわりもそこだと思う。最後の5%が違う」
たとえば彼のサロンのワゴンは、引き出しの裏や奥まで表面と同じ色が塗られ、ワックスがかかっている。
「誰にも見えないですよね。少なくとも合理的ではない。だけどね、それはもうすべて何かをつくる者の原点だと思うんですよ。頭でも同じ。見られないからではなくて、自分がつまんないから、できることはすべてやる。下着と一緒ですよ。誰も見えないけど、ちゃんとしてれば堂々と振る舞える。見えないけど、ちゃんとつくらなければならない」
「ベンツのボンネットを開けた時と、ジャグア(日本語では一般的にジャガー)のボンネットを開けた時にね、コードの配線が違うんですよ。メルセデスは合理的に引っ張ってる。ジャグアはきれいなんですよ。無駄をしてますけどね。でもきれいですよ。ボンネット開けてもきれいだな、と。そこだと思うんですよ。ディズニーランドのつくり方は、ジャグアのボンネット開けた時の配置ですよ」
やはり衿持、であった。
誇るべきものを据える位置。
彼の場合、産業として発達したドイツのメルセデスよりも、クルマ好きが裏庭で自分の好きなクルマをつくり始めた、いわゆるバックヤードビルダーの延長にある英国のジャガー(ジャグア)を美しいと感じる。
「これからの若い世代に、特に美容界に入る人たちに言うとしたら、もちろん外国に行って腕を磨くのもいい。でも土俵に頼るんではなくて、自分が何を表現できるかだと思うんですよ。自己表現の手段が美容だ、と」
「だったら人をきれいにすることが美容ですから、きれいは一種類じゃないんで、自分の表現をトライしてみよう。それでハサミを持ってるんだったらぼくはいいと思うんですよ。そういうのを次の世代、今度は輸出できるような意志を持って欲しい」
「他業種はみんなそれをしている。ソニーにしてもトヨタにしても。でもなんで美容だけが未だに輸入ばかりなのか。輸出がゼロの産業なんてないですよ。じゃ美容に入った人たちが劣るのか。そんなことないんですよ。発想が違うんですよ。輪出しようとしないんですよ。オリジナルをつくろうとしないんですね」
パーク ヤン・スーは、オリジナルをつくった。
それはまず、第1に美容の哲学。第2に作品群。
そして、作品をつくるための道具類や頭髪化粧品、ヘアアクセサリー。
これらはすでに輸出されている。
彼は海外で得た知識や経験を、講習というかたちで日本にフィードバックするのではなく、オリジナルをつくることで「海外に返し」つづけている。
「この間ね、ニューヨークのサロンで仕事をしていた日本人がウチのコームを見て言うんですよ。あ、これボスが使ってた。日本にもあるんですねぇ、って」
最後に、パークはそんな笑い話を披露した。
震源はパーク ヤン・スーである。
マグニチュードは、無限大。
彼の引き起こした津波はすでに、太平洋を軽々と超えている。