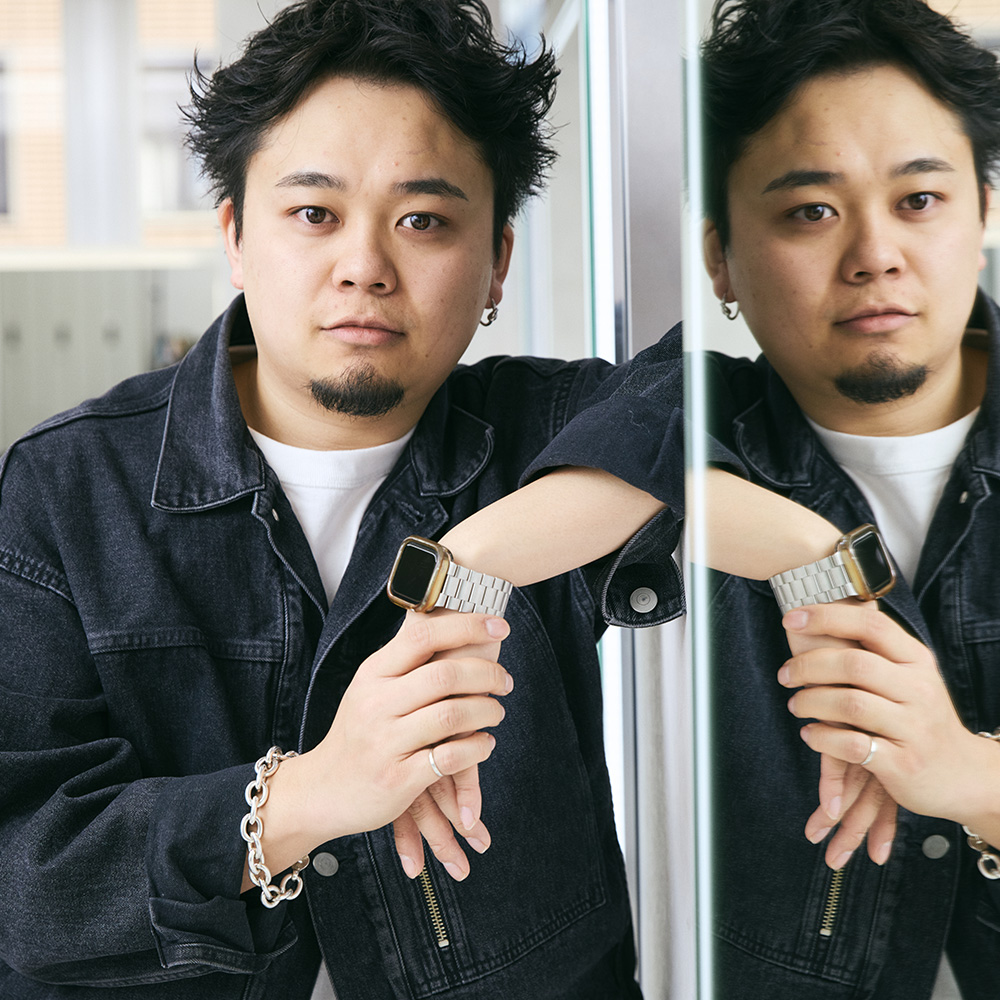さて、どうしよう。
『キャンプGIFU』のゲートを出た大野は、駅に向かって歩きながら考えていた。
(まずは先生や。昼間、キャンプで働くんやで転校しんといかん。定時制やったら第三高校やろか)
岐阜県立第三高等学校には定時制がある。それは大野も知っていた。
両親への話は後回しにした。外堀をすべて埋めてから話す。そうしないと説得できないような気がしていた。
帰宅しても親には何も言わなかった。翌朝、登校すると大野はすぐに職員室へ向かった。
「木暮先生、じつは……」
大野は昨日の『キャンプGIFU』での出来事を話した。木暮は連隊長と同じことを聞いた。
「両親には話したんか」
「はい」
大野はまたウソをついた。
「許してくれたんか」
「はい」
返事をすると、大野は黙った。余計なことを言うと、ウソがバレてしまうような気がしていた。
木暮は大野の目をじっと見つめていたが、やがてこう言った。
「わかった。転校するんやったらオレが証明書を書いたるわ。岐阜で夜間っていったら第三高等学校やわ」
先生の壁は突破した。次は親だ。
帰宅すると、大野はまず母親に話した。母は驚いたが、大野の気持ちを理解してくれた。大野が毎日、朝早くからラジオにかじりついて勉強していることを知っていたからだ。
父が帰宅すると、大野は覚悟を決めた。
「父さん、オレ、アメリカ軍のキャンプで働くことになったで。学校の先生にも話して、定時制に転校する手続きも頼んできた」
父は、ちいさな目をまん丸に見開いて怒鳴った。
「なんでそんなことを、そんな大事なことを勝手に決めとるんや!」
大野は負けなかった。
「これからは英語や。英語がすべてなんや。父さんも知っとるように、オレは英語を勉強してきとる。キャンプにも行って、連隊長にも会ってきたんや」
「連隊長やと?」
「ほうや。キャンプ全体の隊長や」
「会えたんか? 連隊長に。ほんで、会ってどうしたんや」
大野は連隊長とのやりとりをすべて話した。
「ほんじゃあ、ほんとうは働けんのに、とくべつに働けるようにしてもらったんか」
「はい」
父は黙った。まっすぐに大野を見つめている。
「ほうか。本気で決心したんやな。ひとりでそこまで行動したんやな。ほんならええ。わかったわ」
そう言って父は、風呂場へ向かった。その背中はすこし寂しそうだった。
父は染め物職人だった。着物の生地を京染めする職人だった。ほんとうは息子にその仕事を継がせたかった。だが戦争でその仕事は失われた。
父は家族のために川崎航空機に勤めた。あの、各務原飛行場に隣接していた軍需工場である。
戦時中は航空機をつくった。陸軍の航空機を量産した。しかし空襲で工場は徹底的に破壊される。それでも戦後、工場は復活した。設備を大幅に簡素化して、バスの車体をつくる工場に生まれ変わった。
父は慣れない仕事に愚痴ひとつこぼさず取り組んでいた。家族のために黙々と働いていた。その給料は月に8,500円。職人時代の、数分の一に過ぎなかった。
翌週、大野はちいさなバッグに下着や勉強道具を詰めて『キャンプGIFU』を訪れた。もうゲートで立ちすくむことはなかった。ヘルメット姿の衛兵に向かって今度はまっすぐに進むことができた。
「大野です。ウィリアム中佐に呼ばれて来ました」
堂々と英語で語りかける日本人の高校生。その姿に衛兵は驚いたような表情を浮かべたが、すぐに連隊本部に取り次いでくれた。
ジープが、砂ぼこりをまき上げながらやってきた。
「Hi , Mr.Ohno ! Would you ride on ?」
あの、白人大尉。連隊長の副官だった。
『ハウスボーイ』。
それが大野の仕事だった。副官は大野をまっすぐに“職場”へと連れて行った。中隊事務所である。
中隊とは、3〜5つの小隊を束ねる編成で、150人前後の兵を擁する。中隊長は大尉。英語では「Captain<キャプテン>」と言う。
事務所ではその<キャプテン>が、大野の到着を待っていた。
「ミスター・オオノ。君のフルネームはヨシオ・オオノだね」
<キャプテン>は、そう聞いてきた。
「イエッサー」
オオノは即答する。
「よし、じゃあ今日から君のことをヨシオと呼ぶことにする。それでいいかな」
「イエッサー」
「じゃあヨシオ、まずはこの事務所の掃除から始めてくれ。終わったら私のオフィス。最後に将校用のトイレ掃除だ」
「イエッサー」
仕事が始まった。
掃除は得意だった。国民学校でも高校でも、生徒は毎日、教室や廊下、便所の掃除を行っている。だからその手順はすべて身についていた。
すべてが終わると、中隊長は言った。
「オーケー、ヨシオ。いい仕事だ。明日からは独身将校宿舎に行って、ハウスボーイの仕事に就いてくれ」
「イエッサー」
「あ、それから」
そう言って中隊長はクローゼットから一着のジャンパーとズボンを出してきて差し出した。
「これを着なさい」
アメリカ軍の官給品の服だった。階級章こそ付いていないが、立派な軍服だ。大野はありがたく受け取った。
独身宿舎に行っても、仕事は掃除が中心だった。ただそこに洗濯が加わる。洗濯機はなかった。だからすべて手洗いである。
ハウスボーイの日常が始まった。掃除と洗濯を終えると、大野は夕方4時に宿舎を後にする。学校へと向かうのだ。アメリカ軍のジャンパーを羽織った大野は、目立った。しかしだれひとりからかう者はなく、近寄っても来なかった。アメリカ軍は当時、日本では絶対的な権力だった。
名鉄各務原線『運動場前』から終点の『新岐阜』へ。そこで『忠節』行きの市電に乗り換えて、『西野町3丁目』で下車。第三高校の定時制は午後5時30分に始業だ。午後9時15分に授業が終わると、大野はまっすぐにキャンプへ帰営する。就寝は午後11時。そんな生活が始まった。
大野は勉強した。英語だけでなく、他の教科も一生懸命勉強した。それが将来、どんなことに役立つかは考えていなかった。将来、どんな仕事に就きたいかも考えなかった。それよりも今、キャンプで仕事をさせてもらえる。それだけで最高だった。ナマの英語を勉強できるし、メシも食える。これ以上、何を望むというのだ。
しかも給料は1万2,000円だった。調達庁で初めて受け取ったとき、なにかの間違いじゃないかと思ったほどだ。父の給料は8,500円。つまり大野は父の1.5倍近くを稼ぐことになった。その事実を父に打ち明けたとき、父はこう言った。
「ほうか。おまえはオレより稼ぐようになったんか」
そのときも父は、寂しそうだった。
3カ月もたたないうちに、キャンプ内に『インディペンデント・ハウス』が完成した。既婚将校たちが使用するハウス。一戸建てである。その一戸ごとに、日本人のハウスボーイが配置された。
大野もまた、戸建てへと異動になった。本格的な『ハウスボーイ』の仕事が始まったのは、ここからだった。
<Captain Macvoy>
マカボイ大尉。
それが担当する将校だった。マカボイは、自らの仕事を「クォーターマスター」だと言った。略称<Q.M.>。補給係の将校。軍の糧食・被服・燃料などの装備品の責任者。白人。既婚。妻と子どもはアメリカにいるが、近々日本にやってくるという。
マカボイは初対面の大野に笑顔で握手を求めてきた。その手はやわらかく、片手では握れないほど大きかった。
戸建て宿舎の玄関を入ると、広い応接間があった。おそらく20畳はあるだろう。窓際には事務用の机。中央に大きなソファ。その背もたれの向こう側に食堂と台所があった。その食堂も10畳くらいある。台所の脇には大きな白い箱があった。
「これは冷蔵庫だ」
マカボイはていねいに説明してくれる。
「中にあるものはなんでも食べていい。ただし、オレの食事をつくったあとに残ったものなら、だけどね」
マカボイが扉を開ける。大野がのぞき込むと、中にはいろんな食材が入っていた。色とりどりの野菜や肉、チーズやバター。ジュース。牛乳。卵。大野は頭がくらくらして、その場にへたり込みそうになった。
(あぁ、なんてことなんや。これが戦勝国と敗戦国との差なんか。ふつうの軍人の宿舎に、こんなに大きな冷蔵庫がある。その中には食べ物があふれとるやないか)
大野はマカボイが言った言葉を心のなかで繰り返した。
<中にあるものはなんでも食べていい>
また、頭がくらくらした。
敗戦後、日本は悲惨な状況に追い込まれていた。モノはない。食べ物もない。戦時中から米は配給。大豆も配給。マッチも砂糖も配給。衣料品も配給だった。しかもその量は急速に減っていき、戦後になるとごくわずか。しかもしょっちゅう滞っていた。
主食は芋。サツマイモ。だけどそれも配給品でなかなか手に入らない。だから庶民は配給だけでは生きていけない。結局、モノや食料は非合法の“闇市”で手に入れるしかなかった。もちろん安くはない。しかもお金はない。買えるものは限られる。当時の日本人に夢があったとしたら、それはまず何よりも「おなかいっぱい食べられる」こと。しかしそれは文字通り“夢”でしかなかった。
一方、戦勝国の軍人は、同じ日本のなかに住んでいながらこれだけの食料をため込んでいるのだ。
冷蔵庫の前でぼんやりとしている大野を、マカボイが促した。2階へ。そこにはふたつの寝室。廊下の脇にちいさな扉があった。開けるとそこは2畳ほどの細長い空間だった。カーキ色の毛布が乗った軍用ベッドが空間のほぼ全体を占めるように収まっていた。
「ここが君の部屋だ」
マカボイが言った。窓はなかった。部屋の奥には1本の針金が通っていて、そこに木製のハンガーが3つ、ぶら下がっていた。
起床は朝6時である。朝食は6時30分スタート。大野の仕事は朝食づくりから始まった。
マカボイはハウスボーイの仕事をていねいに教えてくれた。まずはクッキング。朝食はトーストにベーコンエッグ。ポークビーンズ。飲み物はトマトジュースかオレンジジュース。ミルクにコーヒー。
冷蔵庫の次に大野が驚いたのはトースターと呼ばれる機械だった。食パンを2枚、トースターの溝に放り込んで、スイッチを押し下げる。すると食パンがトースターのなかに収納される。と同時に、ヒーターに通電する。それだけでも大野は興味津々。こりゃすごい、と思った。だが、ほんとうに驚いたのはその後だ。トーストが焼けると自動的にポンっと、食パンが飛び上がるのだ。大野はそれを皿に載せるだけでいい。
トーストが焼けるまでの間にポークビーンズを缶詰からフォークで掻き出し、鍋に移す。ガスコンロに火をつけ、温める。
ポークビーンズとは、角切りポークと大豆をトマトケチャップで煮込んだもので、大きな缶詰になっていた。軍人はそれを戦場に持っていき、乾パンなどとともに野戦食にするのだ。そのポークビーンズに、マカボイは注文をつけた。
「野戦食にはもう飽きたんだ。できれば味を変えてほしいんだけど」
大野は味の好みを聞いた。マカボイは砂糖とタバスコをテーブルに置いた。まず砂糖で甘みを出す。つづいてタバスコで味の存在感を引き立てる。そのバランスが微妙だった。大野は何度か試すうちに、マカボイの求める味を提供してみせた。希望通りにつくってあげると、マカボイはほんとうにおいしそうに食べるのだった。
人に喜んでもらうことは久しぶりだった。しかも自分の“仕事”が人に評価される。喜んでもらえる。家族ではない。他人に。しかもその他人は日本人ではない。元・敵国のアメリカ人。なのに大野が一生懸命に働くと、笑顔になって感謝してくれるのだ。
人の役に立つことは、たのしい。
大野はそう思った。
人の役に立つことは、うれしい。
それは大野が初めて知った喜びだった。
それまで、大野は自分のために努力してきた。自分の未来を切り拓くために英語を勉強してきた。だれよりも、勉強してきた。
たしかに、英語がアメリカ人に通じることはうれしかった。意思の疎通もできるし、なによりこのハウスボーイという仕事にありつけた。それこそが人生最高の喜びだと思っていた。だけど、それはほんとうの喜びではなかった。
(オレは結局、他人の喜ぶ顔が見たいんや。そっちのほうがうれしいんや)
以来、大野の仕事はますます献身的になった。
マカボイが朝食を摂る間、大野は玄関で靴磨きをする。『KIWI』の靴墨で、マカボイの靴をぴかぴかに磨きあげる。マカボイはその靴を履いて、いつも午前7時30分きっかりに宿舎を出た。
マカボイが出勤すると、大野は自分の朝食をつくる。トーストにミルク。残り物のポークビーンズ。たまにオレンジジュースも少しだけ飲んだ。
食事を終えると食器を洗い、部屋の掃除である。室内は箒で掃く。しゅろの葉を束ねた箒で掃く。
掃き終えると洗濯である。風呂場には大きなバスタブがあり、その中に入って洗濯する。使う道具は日本製の洗濯板に、アメリカ製の固形石鹸。この石鹸が大きいのだ。片手ではつかみきれないくらいほどの大きさ。しかもずっしりと重い。それを鷲掴みにして、マカボイの服にこすりつける。下着もこする。そうして洗濯板の上でゴシゴシと洗うのだ。
お湯を出して石鹸をていねいにすすぐと、絞る。力一杯、絞る。絞ったら庭に干す。干したら、庭の掃除と水まきだ。庭の掃除は竹箒を使う。水まきが終わるころにはもう昼食の時間になっている。大野は冷蔵庫を開けて、余りものを見つけて料理する。
午後の仕事はアイロンがけだ。軍服やカーキ色のワイシャツはもちろん、下着までアイロンをかける。軍服やワイシャツは折り目が命。ワイシャツは背中にタテ3本の折り目をつくる。中央と、左右の肩胛骨から下へまっすぐに。アイロンをかけたらクローゼットのハンガーにきちんとかける。シャツ、ネクタイ、軍服の順に並べる。着用に時間がかからないように、きちんと整理整頓して順番に並べる。
大野はつねにマカボイのことを考えて仕事をした。マカボイの役に立つことを第一に考えた。マカボイの日常が少しでも円滑に、イージーに動くよう全力を傾けた。
仕事はまったく苦にならなかった。それどころかどんな仕事にもやりがいを感じていた。こうすれば、マカボイさんは喜んでくれる。こうすればマカボイさんは仕事に集中できる。
マカボイは、大野の仕事をいつも評価してくれた。マカボイはやさしくて気のいい将校だった。
大野は働いた。懸命に、働いた。料理も少しずつ覚え、キャプテン・マカボイをさらに喜ばせた。
大野の料理を気に入ったマカボイは、よく将校仲間を呼んでパーティーを開いた。大野が用意するのは冷蔵庫で冷やしたビール。ワインとバーボンウイスキー。おつまみにハム、サラミ、フランクフルトソーセージにピクルス。それらを自由に取ってサンドイッチにできるよう、食パンのミミをカットしたものを添えた。さらに生野菜のサラダ。マヨネーズをケチャップと混ぜてレモンやタバスコを加え、トマトの切り身を添えたサザンアイランドをドレッシングにした。
ときどき大野はマカボイにせがまれて、ポークビーンズをつくった。マカボイ用にアレンジした野戦食。それが将校たちにウケた。つくり方を教えてくれ、と何人もの将校が大野に迫った。
こうして「ヨシオ」は、アメリカ軍のド真ん中で急速に受け入れられていくのであった。
つづく
☆参考文献
『超訳 日本国憲法』池上彰 新潮新書
『ヴィダル・サスーン自伝』髪書房
『Vidal Vidal Sassoon The Autobiography』PAN BOOKS
『ヴィダル・サスーン』(DVD) 角川書店